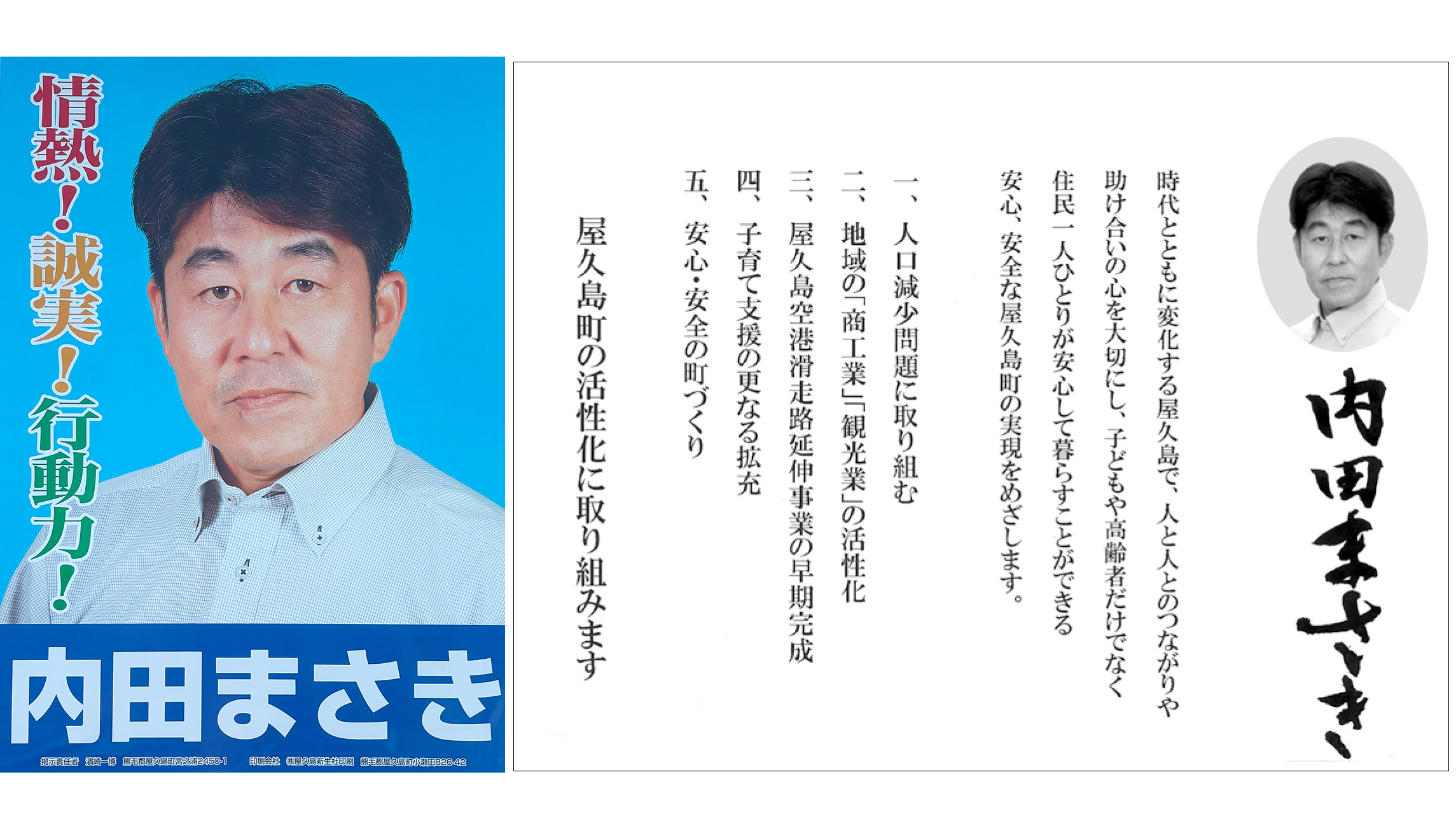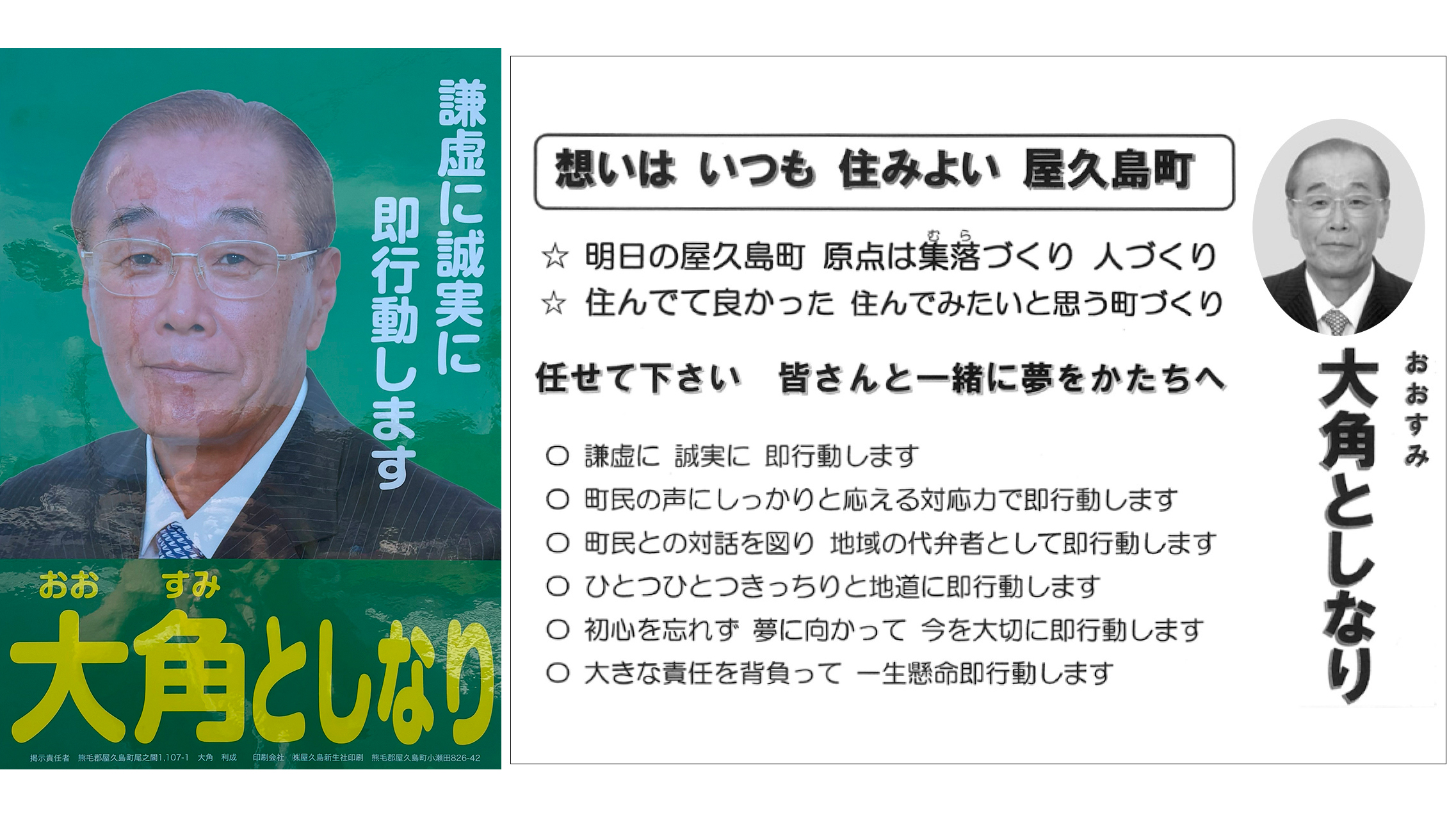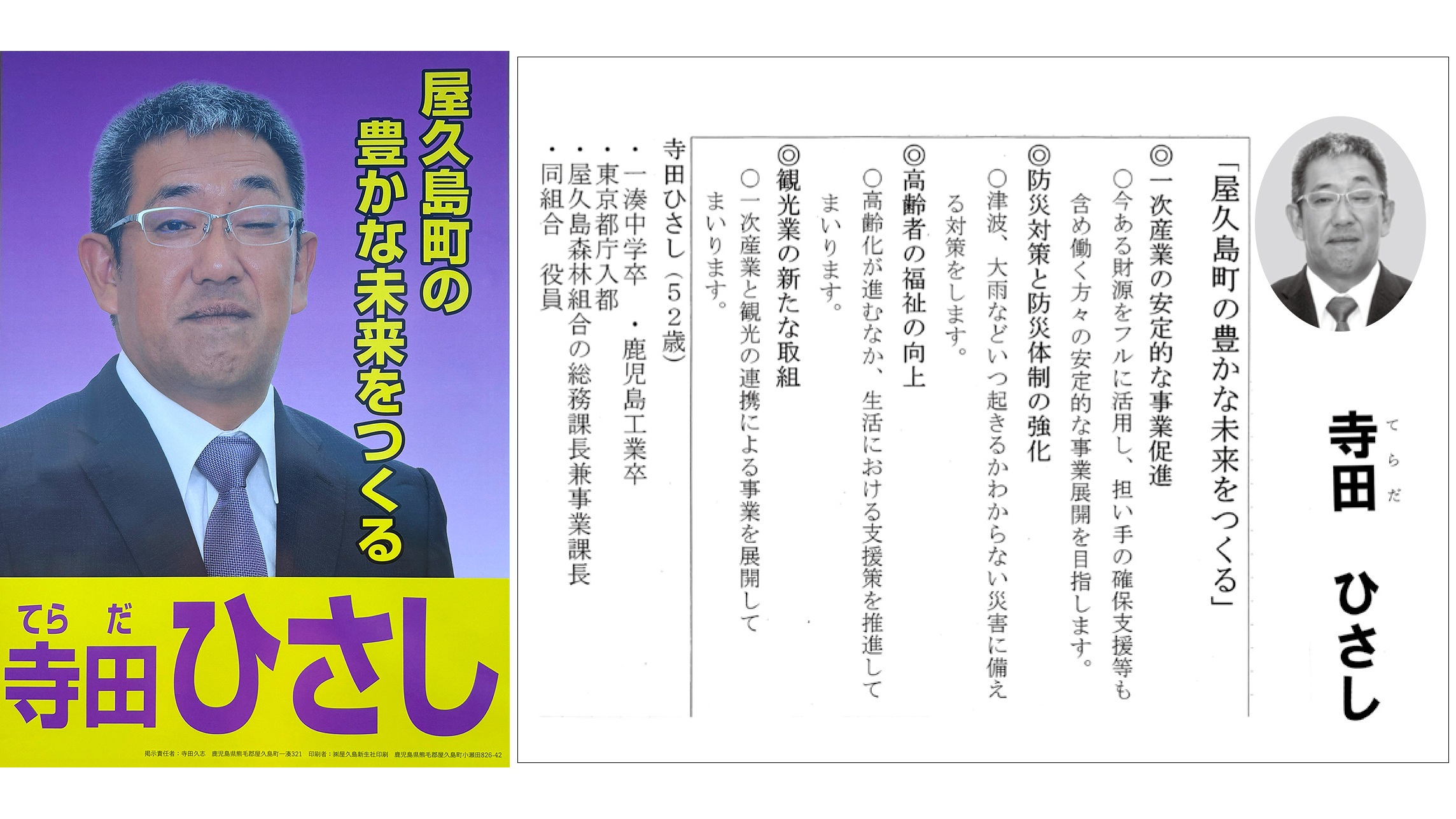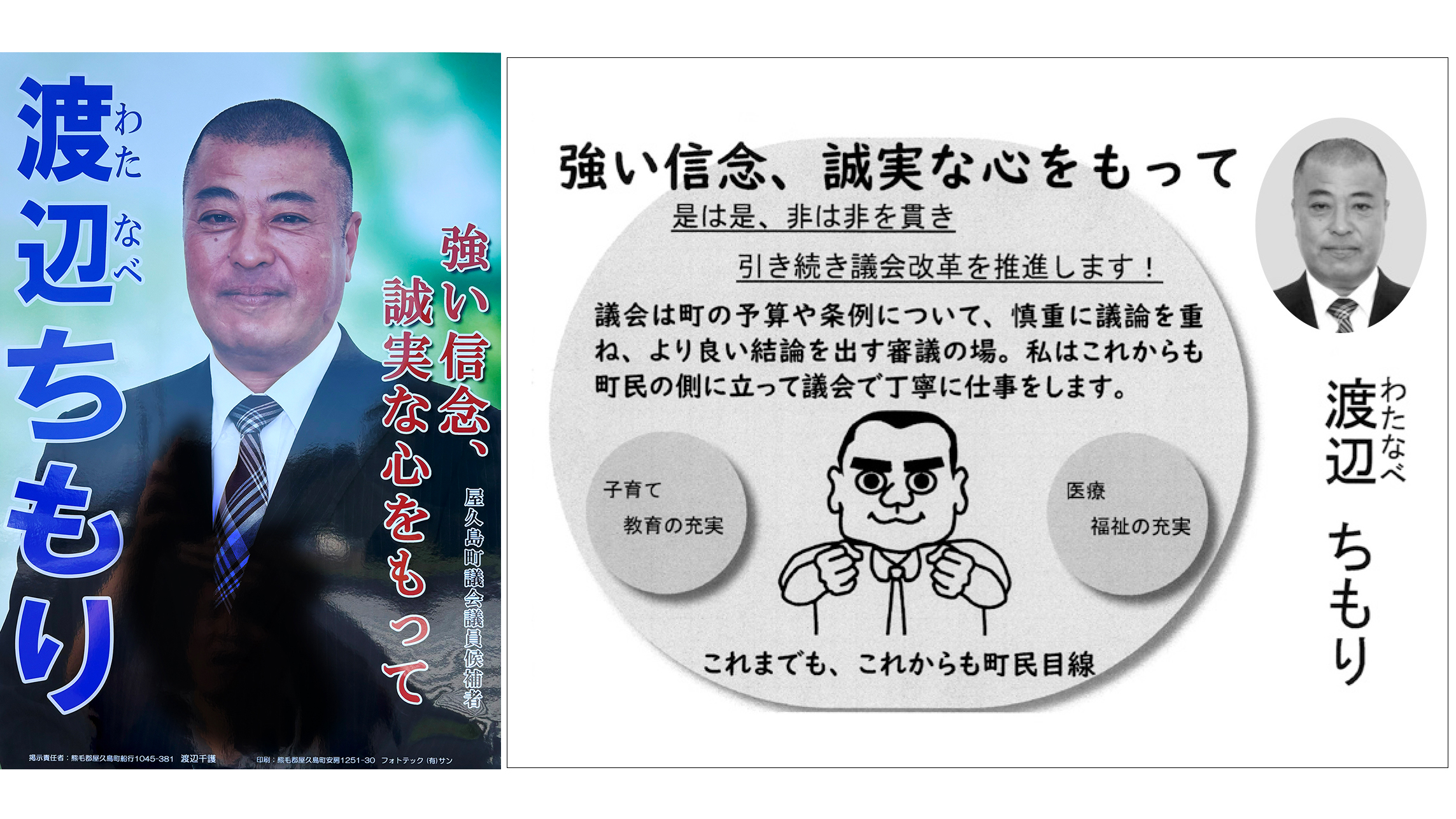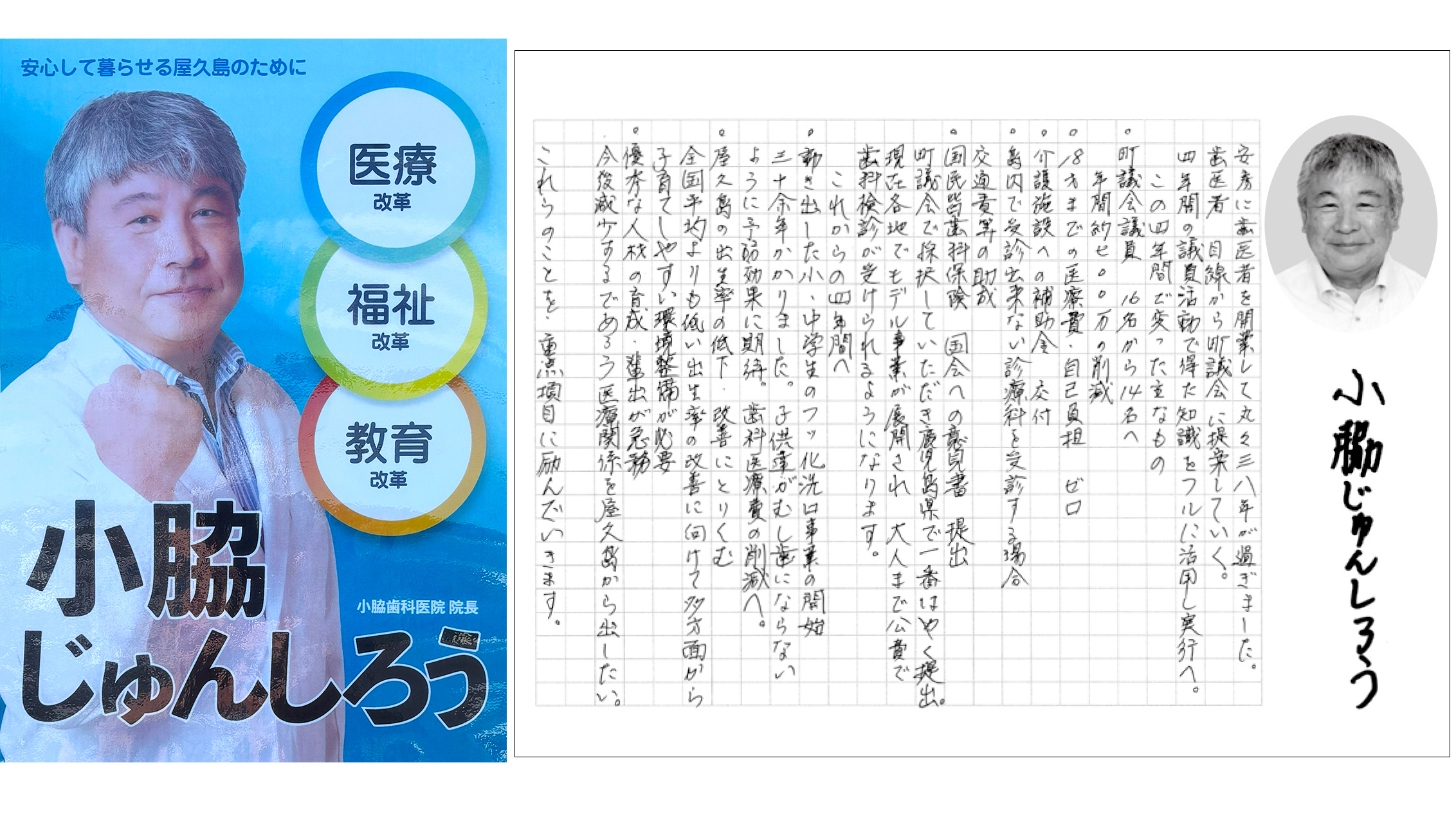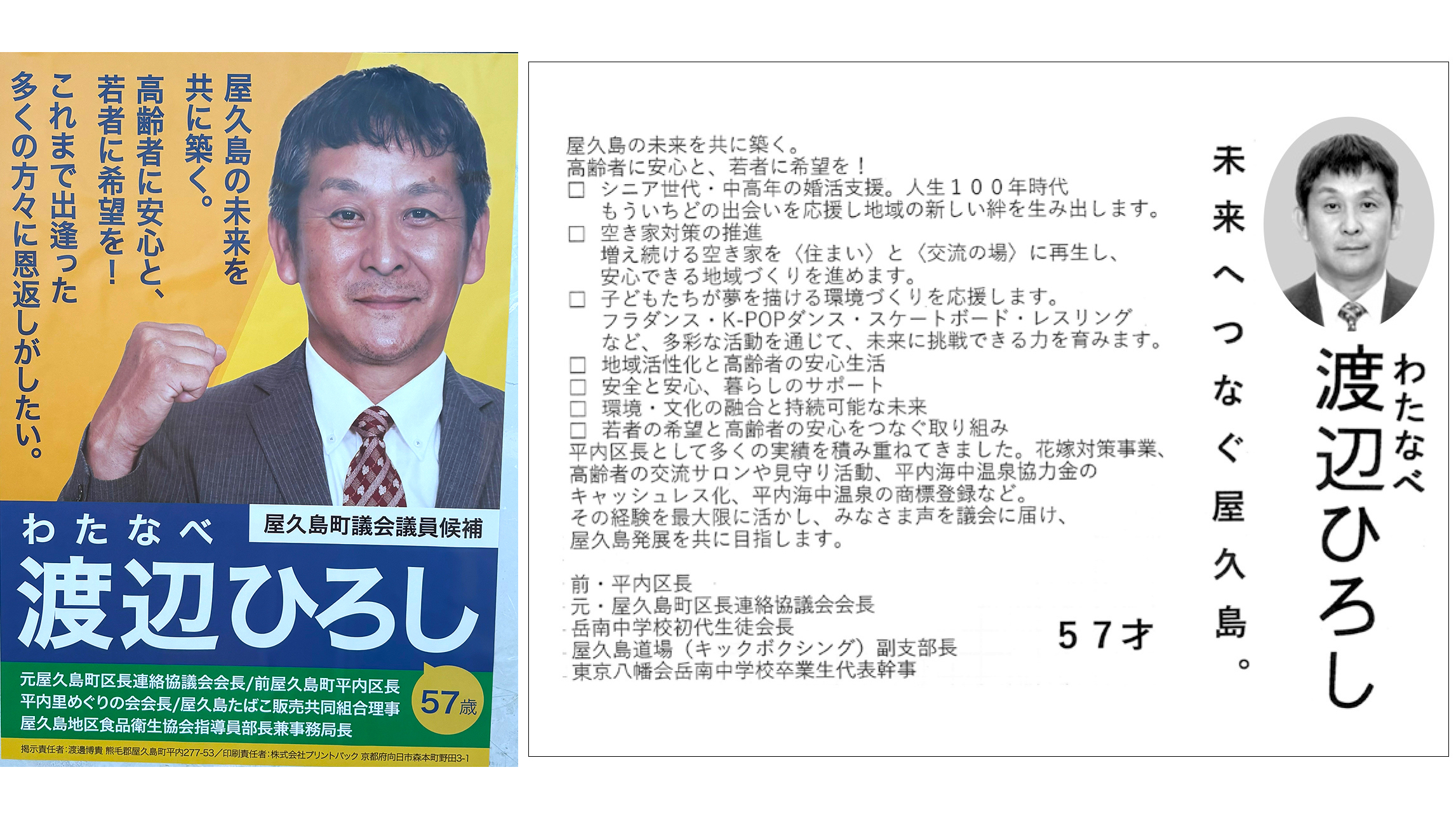【視点】過去最低の投票率に沈んだ屋久島町議選
投票率74.18%、有権者の関心薄れ 初めて80%台を割り込む

屋久島町議選が9月21日に終わったが、その投票率の低さに驚かされた。
<74.18%>
旧上屋久町と旧屋久町の合併後にあった町議選では、新型コロナウイルスの感染が拡大していた2020年5月の補欠選挙を除いて、最も低い数字である。
・2009/09/20 88.91%
・2011/10/30(補欠) 86.42%
・2013/09/22 83.54%
・2017/09/17 82.62%
・2020/05/10(補欠) 69.43%
・2021/09/19 81.76%
・2023/10/29(補欠) 81.22%
・2025/09/21 74.18%
定期選挙の投票率だけをみると、今回は初めて80%台を割り込み、前回の2021年からは7.58ポイント下回った。最も高かった2009年と比べると、実に14.73ポイントも下がっており、この16年で町議選に対する町民の関心が薄れていることがわかる。
記念撮影-1-1024x576.jpg)
屋久島町議選の当選証書附与式が終わったのちに記念撮影する14人の新町議たち=2025年9月22日、屋久島町役場・議会棟、屋久島ポスト撮影
失われた663票があれば……
それでは今回の町議選で、どれほどの有権者が投票に行かなかったのか。
・有権者数 9419人
・投票者数 6987人
・棄権者数 2432人
もし投票率が100%であれば、さらに2432人が投票していたことになるが、それは現実的ではない。そこで、今回の投票率が2021年と同じ81.22%だったとすると、次のような数字が浮かび上がってくる。
・有権者数9419人×81.22%=7650人
・有権者数9419人×74.18%=6987人
・7650人-6987人=663人
もし前回と同じ投票率であれば、さらに663人が投票していたことになる。
投票箱に入ることがなかった663票は、決して小さくない数字だ。今回、最も多い得票数は石田尾茂樹氏の618票だったので、優に1人をトップ当選させられる票が失われたことになる。さらに候補者16人で頭割りすれば、1人あたり41票ほどになるので、各候補の当落や当選順を大きく左右する票の数である。
石田尾茂樹氏-1024x499.jpg)
屋久島町選挙管理委員会の委員長(左)から当選証書を受け取る石田尾茂樹氏(中央)=2025年9月22日、屋久島町役場・議会棟、屋久島ポスト撮影
新たな4年で町民の期待を集められるか?
なぜ今回、これほど多くの有権者が投票に行かなかったのか?
推察にはなるが、議員定数14に対して、立候補したのが現職12人と新人4人の計16人だったので、「自分が投票しても、これまでの議会と何も変わらない」と思った人が多かったのか。それとも、単に屋久島町政に関心のない有権者が増えただけなのか。
いずれにしても、町長選を含めた定期選挙で投票率が80%を割り込んだのは、今回が初めてである。そして一つ、はっきりと言えるのは、屋久島町議会に期待して、関心を寄せる有権者が大きく減っているということだ。
要するに、「誰が町議になっても同じ」ということである。
10月1日には臨時議会が開かれ、今回当選した14人が新たな一歩を踏み出すことになる。多くの町民から関心を寄せられる町議会になるためには、どうすればいいのか。
これから始まる4年の任期に期待をしつつ、しっかりと各町議の言動を見守っていきたい。


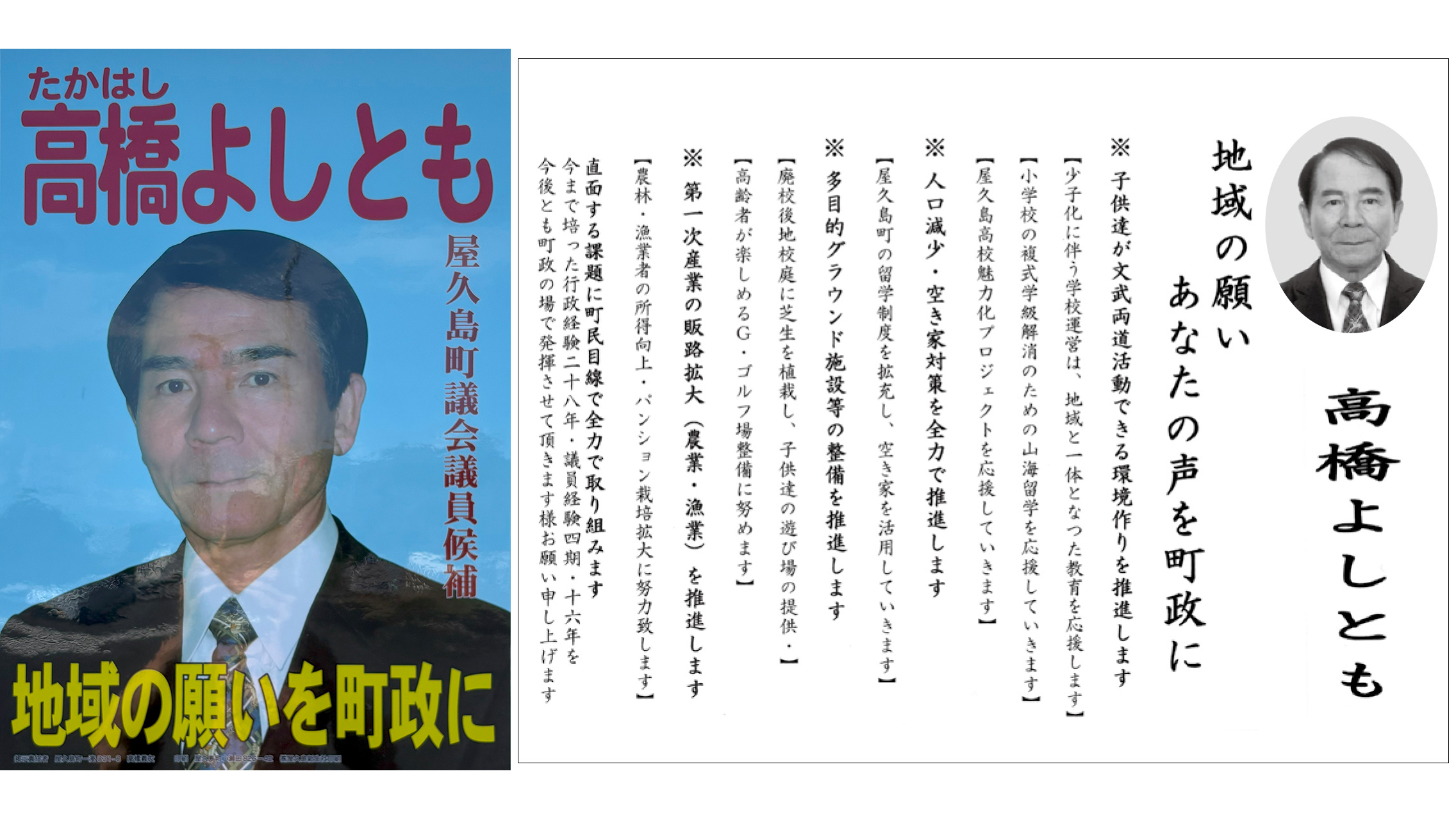
記念撮影.jpg)