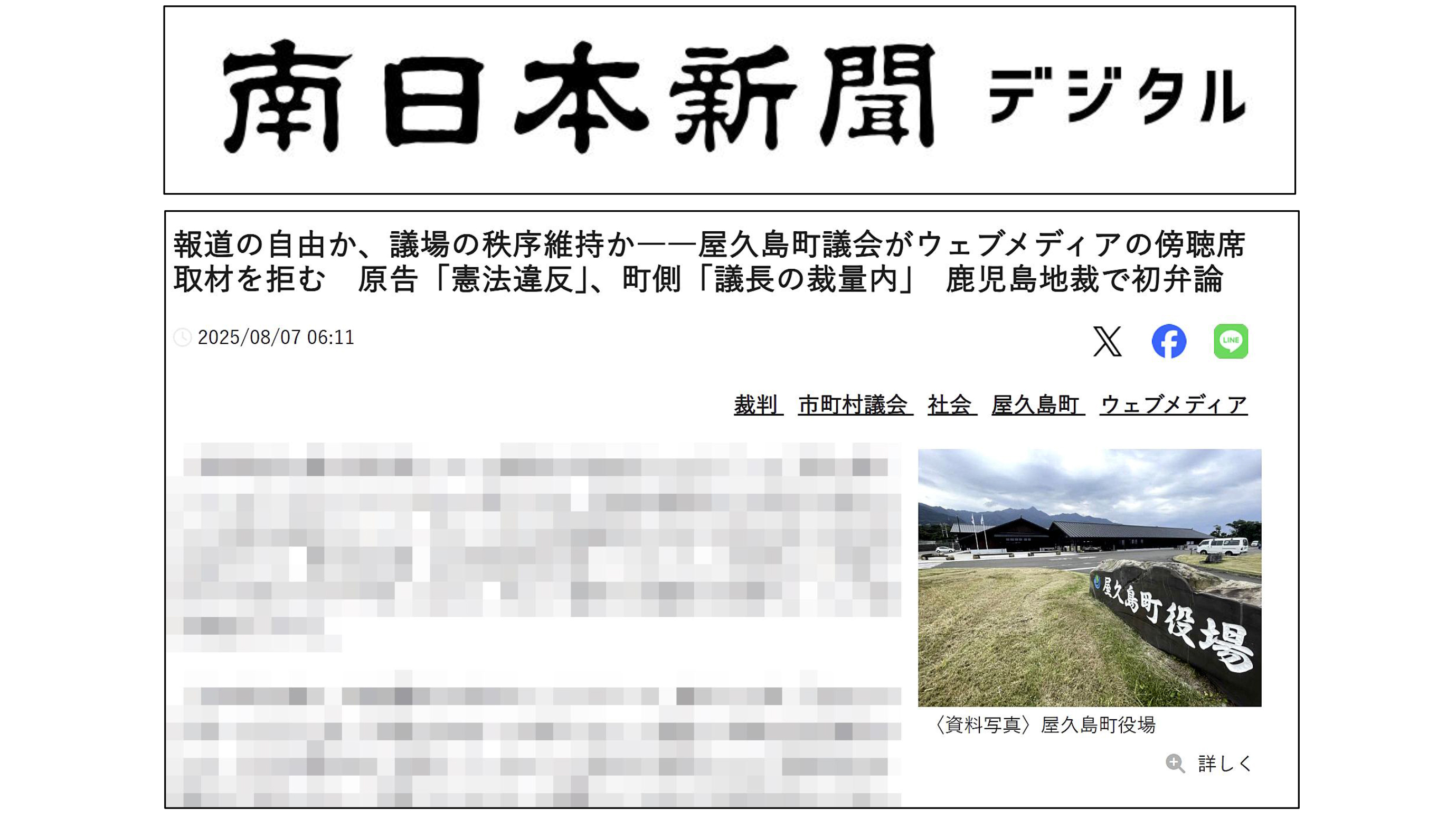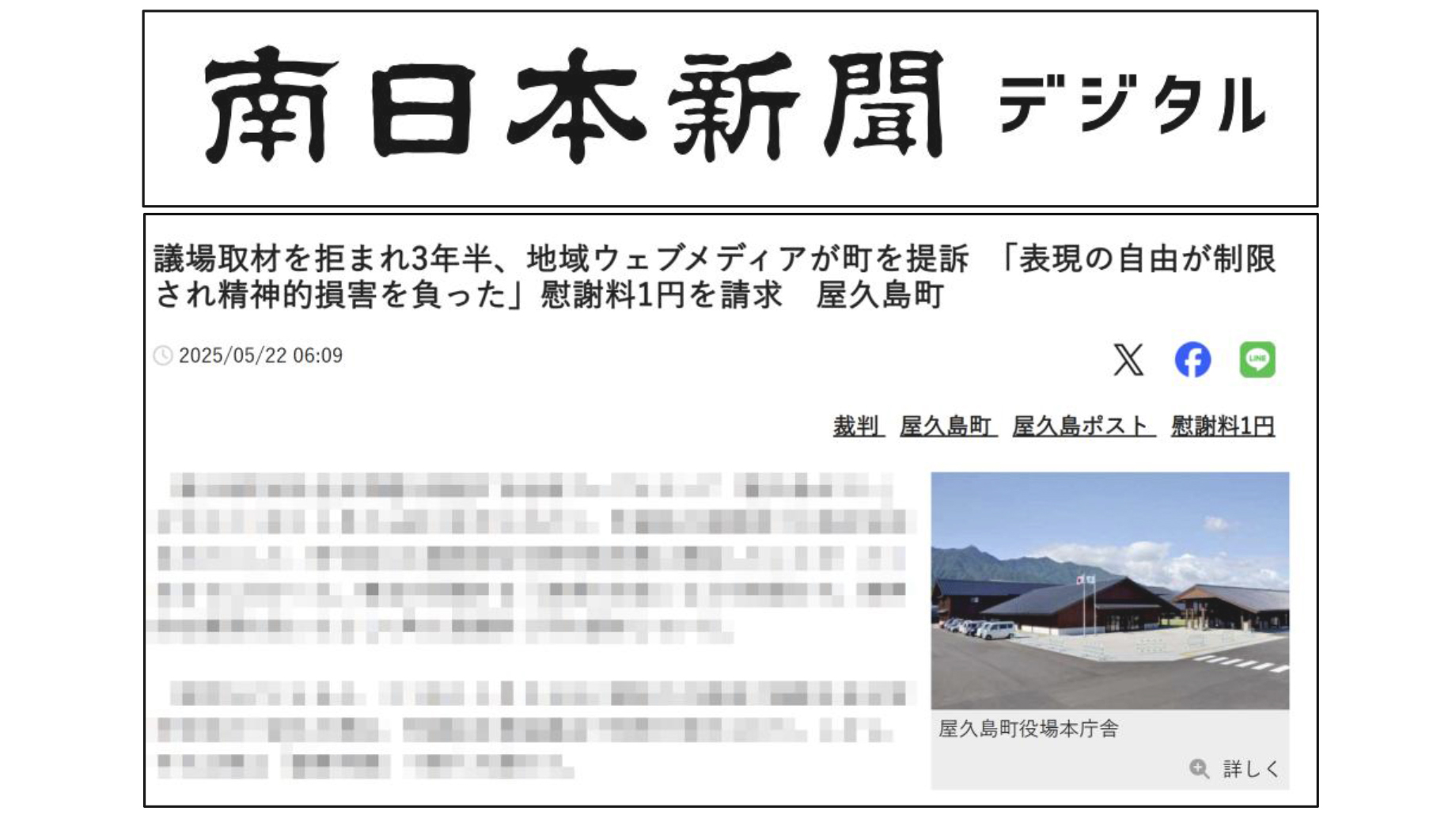ポスト反論、合理的理由なき議会取材の禁止【議会取材の自由を守る訴訟】
石田尾議長、日本新聞協会など加盟を許可条件 → ポスト「法の下の平等」に反する差別的判断
町、取材禁止したのに「表現の自由は制限していない」!?

屋久島町議会(石田尾茂樹議長)が市民メディア「屋久島ポスト」の議会取材を拒否しているのは、「表現の自由」などを保障した憲法に違反しているとして、屋久島ポストが町を相手取って提起した「1円訴訟」――。
この訴訟の第1口頭弁論が8月6日に鹿児島地裁であり、原告の屋久島ポスト側には争点を明確にするようにとの「宿題」が出されました。それを踏まえ、私たちは8月12日付で「原告第1準備書面」を送付し、この訴訟における争点を明らかにしたうえで、被告町が7月31日付で提出した答弁書に反論しました。
まず、本訴訟の争点については、次の3点としました。
・屋久島ポストが2021年12月7日、国庫補助金の不正請求問題を報道するために、屋久島町議会12月定例会の本会議を取材しようとした際に、石田尾議長から議場での取材(撮影と録音)を禁止されたこと。
・屋久島ポストが2023年8月28日、現職町議が罰金50万円で有罪となった廃棄物の不法焼却事件について、同町議が事件の事情説明をする同町議会の全員協議会を取材しようとした際に、石田尾議長から取材を禁止されたこと。
・石田尾議長の判断によって、屋久島ポストが2021年12月7日から2025年4月18日までの約3年半にわたり、同町議会の本会議および全員協議会の取材を禁止されたこと。
これらの争点を踏まえ、石田尾議長の違法行為については、次の主張をしました。
・本会議と全員協議会の取材禁止については、「法の下の平等」を保障した憲法14条1項および「表現の自由」を保障した憲法21条1項に違反した判断である。
・議会取材の禁止によって、屋久島ポストの共同代表らが負った精神的な損害を賠償する法的責任については、国家賠償法1条1項及び民法709条が適用される。

議員席から取材を拒否する理由を問われた後、手を出して町議の発言を制止する屋久島町議会の石田尾茂樹議長=2021年12月7日、屋久島町役場議会棟
以上の争点を明確にしたうえで、私たちは町が提出した答弁書に対し、次のとおり反論しました。鹿児島地裁に提出した原告第1準備書面から、その要旨を伝えます。
*
第1 憲法14条違反について
1 正確かつ公平に報道できる能力と資質
屋久島町は答弁書で、石田尾議長が日本新聞協会や日本民間放送連盟の加盟社に限って、議場での取材を許可していることについて、「これらのメンバーであれば、組織的に事実を正確かつ公平に報道することが出来る能力、資質を備えている報道機関であることが制度的に担保されているとみることに相応の合理性がある」と主張している。
この主張を逆に解釈すると、同協会や同連盟に加盟していない報道機関や出版社、記者、ライターなどは、「事実を正確かつ公平に報道することが出来る能力、資質を備えていない」ということになる。
しかし、屋久島ポストを含めて、同協会や同連盟に加盟せずに報道している記者らは全国に数多くいて、インターネットや雑誌などの媒体で「事実を正確かつ公平に報道」している。それにもかかわらず、石田尾議長は同協会と同連盟に加盟していない記者らを一律に「能力と資質がない」と断じて、議場での取材を禁止しており、この差別的な判断こそが、「法の下の平等」を保障した憲法14条に違反しているといえる。
議場取材を認めるか否かについて、屋久島町は「議長に広範な裁量が認められている」と主張している。しかし、その裁量権を行使して市民の活動を制限する場合、議長にはその理由を明確に説明する責任があり、さらには、その理由に合理性がなくてはならない。
これを屋久島町議会のケースでみると、石田尾議長は、屋久島ポストが同協会などに加盟していないことを理由に、屋久島ポストの取材を「報道とは認めない」と断じたが、先述したとおり、それだけを根拠にしても、屋久島ポストの取材を禁止する理由には到底なり得ない。ここで重要なのは、町も指摘しているとおり、「事実を正確かつ公平に報道することが出来る能力、資質を備えている」か否かであり、それはすなわち、屋久島ポストにその能力と資質があるかどうかということである。
訴状で示したとおり、屋久島ポスト共同代表の武田剛は朝日新聞社で20年の取材経験があり、2012年に退職して屋久島町に移住したのちには、KKB鹿児島放送と朝日新聞の屋久島駐在をした経験もある。両社と契約していた2015年から2020年にかけては、新聞とテレビで町議会の報道もしており、当時から現職議員であった石田尾議長は、武田が「事実を正確かつ公平に報道することが出来る能力、資質を備えている」ことは十分に認識していた。
また、2021年11月26日に開かれた全員協議会において、石田尾議長は「今回限りの特例」として屋久島ポストの取材を許可したが、それによって屋久島ポストが議会での審議を歪めるような報道をした事実は一切ない。さらには、2025年4月18日に屋久島ポストの議会取材が一転して許可されたことからも、屋久島ポストが正確かつ公平な報道ができることを、石田尾議長が認識していたことは明らかである。
つまり、屋久島ポストが2021年12月7日に議会取材を禁止された、そもそもの時点で、石田尾議長には屋久島ポストの議会取材を禁止する合理的な理由はなかったということである。
よって、屋久島ポストの議会取材を禁止した石田尾議長の判断は、議長の裁量権を大きく逸脱したものであり、「法の下の平等」を保障した憲法14条1項に違反していることは明らかである。
2 屋久島ポストが議会に与えた不利益について
町は答弁書で、屋久島ポストが法人格を有していないことを理由に、石田尾議長が議会取材を禁止したことについて、「法人組織か否かという点は、法人組織であれば複数の構成員が存在するのが通常であり、かつ、責任の所在も明確であることから、複数の目で、しかも組織的に、事実を正確かつ公平に報道できる期待が高まるといえる」と主張している。
そこで、ここでもこの町の主張を逆に解釈すると、法人格を有しない記者やライターによる取材は、「責任の所在が不明確」で「事実を正確かつ公平に報道できる期待が低い」ということになる。
しかし、屋久島ポストを含めて、法人格を有していなくても、「正確かつ公平な報道」をしている記者やライターは全国に数多くいる。また、屋久島ポストを含めて、自身の顔と実名をさらして取材をしている記者やライターも全国に数多くいて、その報道に事実誤認などの問題があれば、取材者個人として、しっかりと責任を負うことになる。
つまり、法人でなくても、「正確かつ公平な報道」は可能であり、何か問題が発生した際には、「責任の所在」を明確にできるということである。民間組織ではない公的な屋久島町議会が、取材の許可を求める記者やライターに対し、法人格を有していないことを理由に取材を禁止することは、「法の下の平等」を保障した憲法14条に反する判断だといえる。
石田尾議長が議会取材を禁止した理由について町は、屋久島ポストが日本新聞協会や日本民間放送連盟に未加盟で、法人格を有していないことを挙げているが、屋久島ポストが町議会に与えた、または、与えることが予見できる「不利益」については、何ら具体的に言及していない。先述したとおり、屋久島ポストに「正確かつ公平に報道する能力と資質」があることは明らかであり、それについては、石田尾議長も十分に認識しているところである。
よって、今後も町が同様の主張を続けるのであれば、一般論ではなく、屋久島ポストが町議会に与えた、または、与えることが予見できる「不利益」について、具体的に主張及び立証することを強く求める。

一転して取材が許可され、屋久島町議会の議事を進める石田尾茂樹議長を撮影する屋久島ポストのビデオカメラ=2025年6月20日、屋久島町議会
第2 憲法21条違反について
1 「表現の自由」と「取材の自由」
屋久島町は答弁書で、「本件で問題となっているのは、撮影・録音という取材の制限であり、特に原告らが報道という表現活動をすること自体を制限したものではないのであるから、『取材の自由』の制限のみが問題となっていることを認識すべきである」と主張している。
町による憲法解釈は別にして、日々、取材と報道の活動を続ける屋久島ポストとしては、この町の主張は、極めて的外れであると言わざるを得ない。記事を自由に書いて報道する、すなわち「表現の自由」を守るためには、その前段で「取材の自由」が保障されなくてはならない。なぜなら、自由に取材ができなければ、自由に記事が書けないからである。それゆえに、「取材の自由」と「表現の自由」は連続した活動であり、両者は不可分な関係にあるといえる。
また、町は「本件においては、議会における撮影・録音行為を制限しているのみであり、メモ等を取ることを制限しているものではなく、取材活動が完全に制限されるわけではなく、限定的な制限だといえる」と主張している。
この町の主張も、取材と報道を続ける記者らの立場を顧みない、極めて失当なものである。町は「撮影・録音行為を制限しているのみ」と指摘するが、議会の様子を「正確かつ公平に報道」するには、メモだけでは不十分であり、議場での撮影と録音は必要不可欠である。もし誤ってメモをした場合、映像や録音で確認できなければ、それこそ町が重要視する「正確かつ公平な報道」ができなくなる。
さらに町は、「しかも、議会は役場内に設置されたモニター画面で中継されており、議場内にいなくても撮影・録音は可能である。事実、原告らは役場のモニターを撮影・録音したうえで、 これらを発信している」と主張している。
それでは逆に問いただすが、なにゆえに、石田尾議長は屋久島ポストの議場取材を禁止してきたのか。役場内に設置されたモニター画面で撮影と録音ができるのであれば、屋久島ポストが議場で撮影しても同じことである。そして、武田の過去の取材実績からも、屋久島ポストが撮影と録音で議事を妨げることは予見できず、石田尾議長が議場取材を禁止する合理的な理由はなかったといえる。
また町は、2025年4月18日に屋久島ポストの議会取材が許可されたことについて、「原告らの取材の自由が制限されなくなったのであるから、原告らに何らの損害・不利益はない」と主張している。
しかし、2021年12月7日から約3年半にわたり、石田尾議長が屋久島ポストの議会取材を禁止してきた事実に変わりはなく、それによって屋久島ポストに「損害・不利益」があったことは明らかである。また、石田尾議長が出した取材許可の期限が2025年9月30日であることから、それ以降に再び屋久島ポストの議会取材が禁止される可能性もある。
なお、町は憲法21条が保障する「表現の自由」をめぐり、石田尾議長が制限したのは「取材の自由」であり、「表現の自由」は制限していないと主張している。そして町は、この訴訟では「憲法21条の表現の自由に対する制限の許容性に関する厳格な基準によって検討する必要性は無い」と断言している。
しかし、先述したとおり、報道取材における「取材の自由」と「表現の自由」は不可分の関係にあり、両者を別々に論じることはできない。町は独自の憲法解釈によって、両者を別々に扱っているが、この訴訟で争っているのは、屋久島ポストの「取材の自由」が制限され、その結果として、「表現の自由」が侵害されたということに対する違憲性である。
よって、石田尾議長による議会取材の禁止は、憲法21条1項が保障する「表現の自由」を侵害するものであり、その違憲性を審理するにあたっては、石田尾議長による議会取材の禁止に「厳格な合理性」があるか否かを判断する必要があるといえる。
2 合理的な理由がない取材制限
町は答弁書で、石田尾議長が屋久島ポストの取材を制限した目的は、「会議の秩序を維持し、公正かつ十分な審議を確保することにある」と主張している。
しかし、過去に武田がKKB鹿児島放送と朝日新聞の取材で、「会議の秩序」を乱したことはなく、「公正かつ十分な審議」の確保を妨害したこともないことから、屋久島ポストが取材で議会に不利益を与える可能性はなかったといえる。それゆえに、石田尾議長が屋久島ポストの議会取材を禁止する合理的な理由がなかったことは明らかである。
また、町は「撮影された映像は、その一部を切り取ったり、編集を加えたりすることで実際の議事内容と異なる印象を与えることも可能であり、不正確かつ公平・公正を欠く発信がされることがあり得る」「議事内容や議員活動とは関係ない議員や参考人、他の傍聴人のプライバシーに関する事項などについて撮影・発信されることも、現実的な可能性として想定される」と主張している。
しかし、これらの町の主張は、あくまでも一般論で、その可能性があると指摘するものであり、過去の武田の取材実績を踏まえれば、屋久島ポストには該当し得ないものである。
もし仮に、過去の報道で武田が議会で撮影した映像について、「その一部を切り取ったり、編集を加えたりすることで実際の議事内容と異なる印象を与え」たことがあれば話は別だが、そのような事実は一切ない。また、武田が「議事内容や議員活動とは関係ない議員や参考人、他の傍聴人のプライバシーに関する事項などについて撮影・発信」したこともないことから、町の主張は失当であると言わざるを得ない。
さらに町は、議会報道で「不正確かつ公平・公正を欠く情報発信」がなされることによって、「議員らが自由な討論をすることを控えるような萎縮効果」を与えたり、「自由な議論の場であるはずの議会の機能が喪失」させてしまったりするなどとして、累々とその危険性を強調している。しかし、過去の議会取材で武田がそのような不利益を町議会に与えた事実はなく、これら町の主張も屋久島ポストの議会取材には該当しないといえる。
つまり、石田尾議長には、屋久島ポストの議会取材を禁止する合理的な理由はなかったということであり、町が答弁書で示した一連の主張は、屋久島ポストの取材では想定されない事態を、一般論として持ち出しているに過ぎない。
よって、石田尾議長が屋久島ポストの議会取材を禁止する合理的な理由はなく、それが結果として、憲法21条1項が保障する「表現の自由」を侵害していることは明らかである。
3 取材制限の説明責任について
町は答弁書で、2025年4月に石田尾議長が屋久島ポストの議会取材を一転して許可し、その理由を「傍聴席からの撮影・録音等については、屋久島町議会傍聴規則第9条の規定により、議長の許可要件であることから、この規定により不許可及び許可の決定を行っております」と屋久島ポストに説明したことについて、「まさに広範な裁量権を有する議長の説明として必要かつ十分な説明なのであり、 何ら説明責任違反はない」と主張している。
しかし、行政機関によって自身の活動を制限された一般市民が、このような説明だけで納得できるはずはなく、屋久島ポストとしては、到底受け入れることはできない。一度は2021年12月7日に議会取材が禁止されたのち、それが一転して2025年4月18日に許可されたのであれば、なぜ、どのように「議長の判断」が変わったのかを説明するのは、石田尾議長に課せられた当然の責務であるといえる。
第3 石田尾議長による自らの説明
町は答弁書で、石田尾議長が屋久島ポストの議会取材を禁止した理由について累々と述べているが、そのすべてが一般論として心配される町議会への不利益であり、個別のケースである屋久島ポストの議会取材には該当しないものである。
実際には、屋久島ポストは町議会に不利益を与えておらず、武田による過去の取材でも、町議会に不利益を与える可能性を予見できる事実は一切ない。さらには、2025年4月18日に石田尾議長が屋久島ポストの議会取材を一転して許可したのち、屋久島ポストは町議会6月定例会を議場で取材したが、町が危惧するような問題は何ら一切起きていない。
これらの事実を踏まえると、石田尾議長および町は、屋久島ポストが町議会に与えるはずがない不利益を、殊更に一般論として強調して、あたかも屋久島ポストが町議会に悪影響を及ぼすかのごとく主張しているに過ぎない。
よって、今後も町が同様の主張を続けるのであれば、一般論ではなく、屋久島ポストが町議会に与えた、または、与えることが予見できる「不利益」について、石田尾議長による自らの説明によって、具体的に主張および立証することを強く求める。
以上