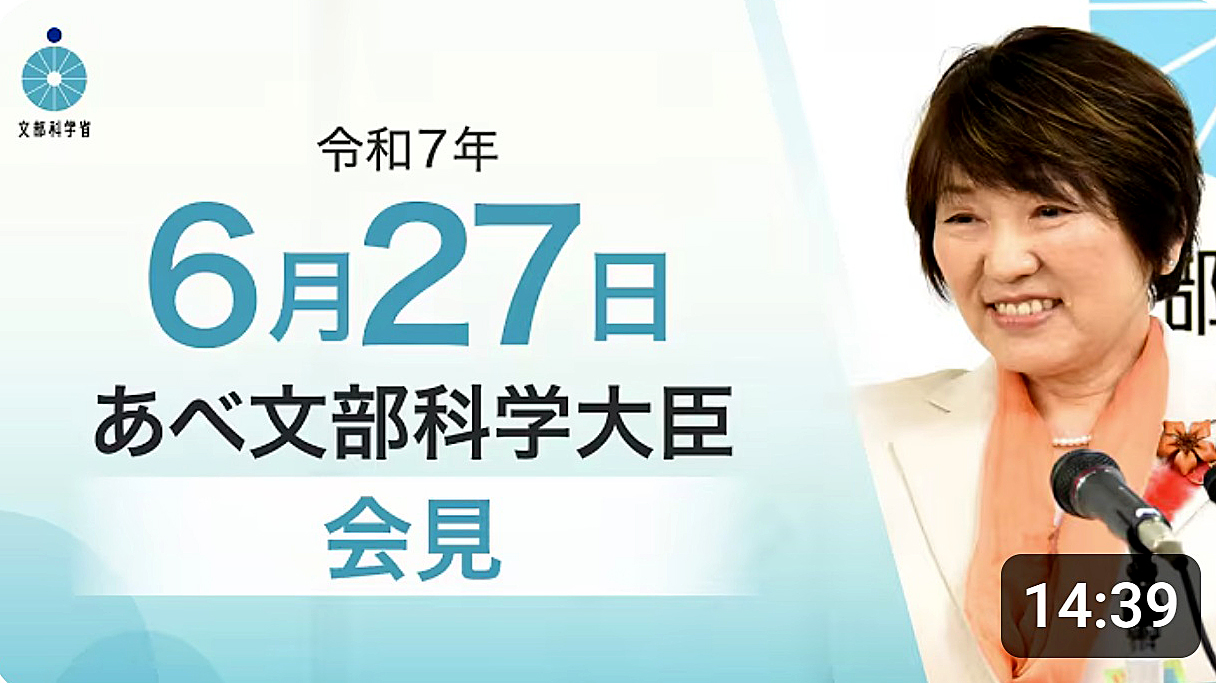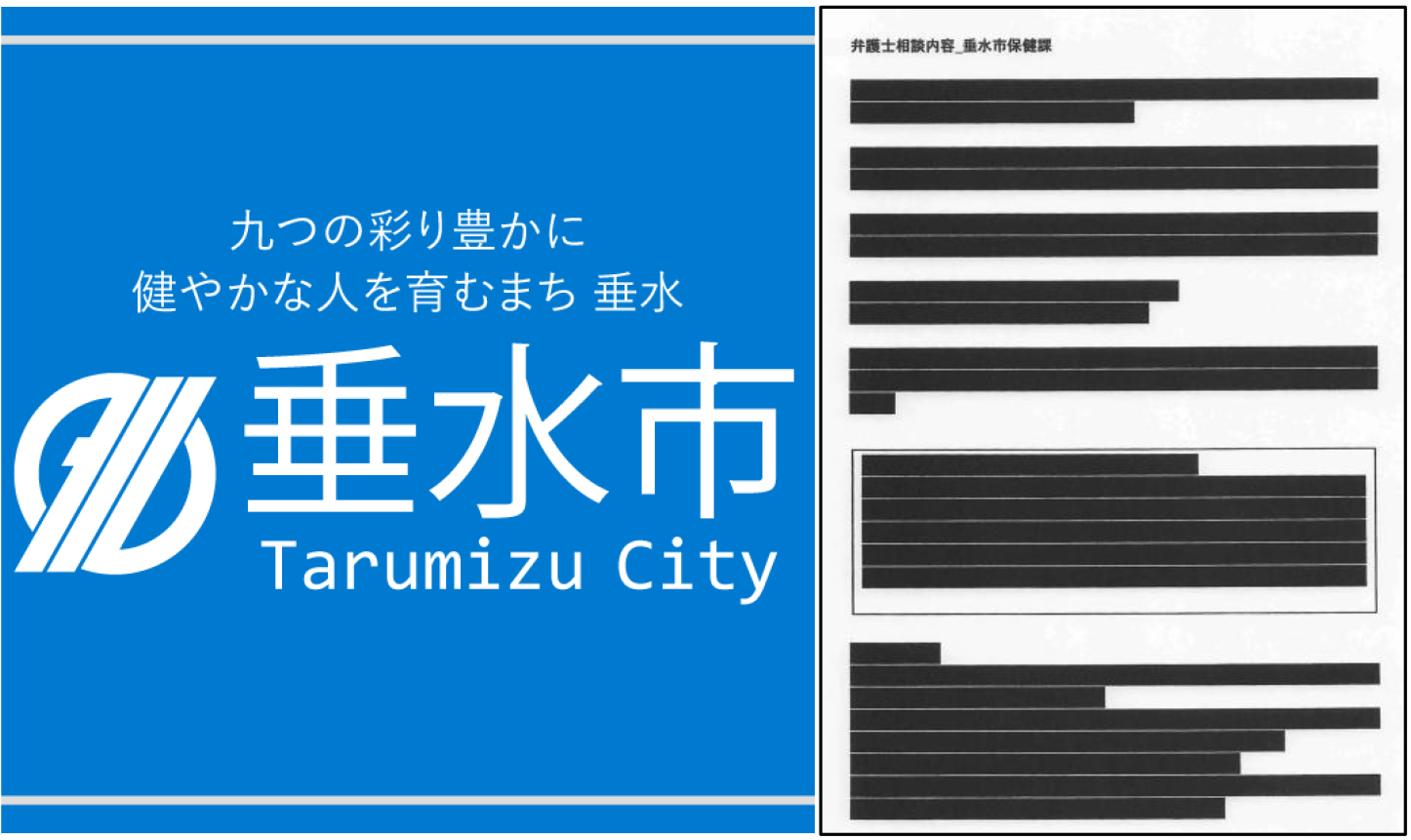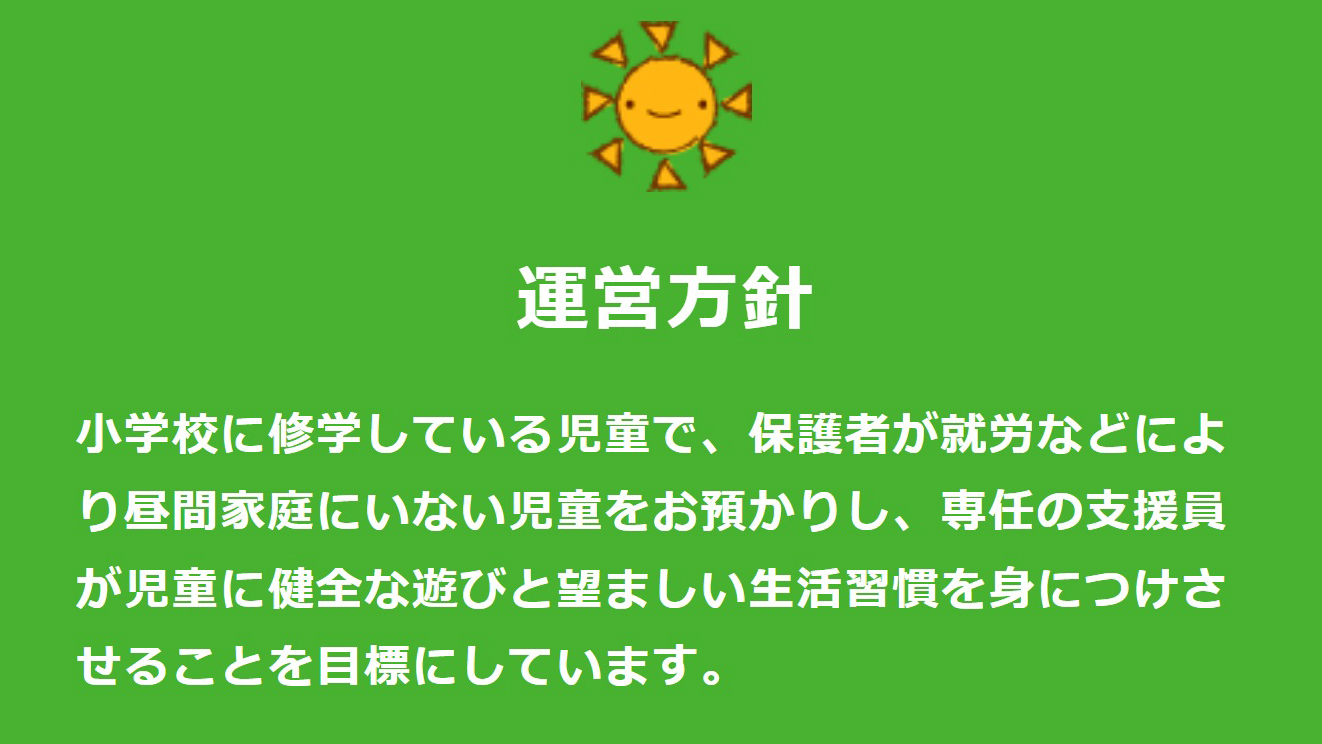視点】児童盗撮事件、垂水市に指導できない国と県/鹿児島ポスト
文科省、学校での盗撮事件で都道府県などの教育長と緊急会議 → こども家庭庁と鹿児島県、児童施設の盗撮事件は垂水市に対応を一任
県子育て支援課「学校とは法律や制度が違う」

【左】垂水市のウェブサイトに掲載された市のマークなど
教員による盗撮などの性暴力事件が相次いでいることを受けて、文部科学省は7月10日に緊急のウェブ会議を開き、都道府県と政令指定都市の教育長に対し、再発防止策の徹底や服務規程の厳守などを求めた。
朝日新聞の報道(7月10日付)によると、文科省の初等中等教育局長は「非常に耳を疑う、教育界を揺るがすような大変由々しき事態。危機的な状況だと共有していただき、教師による性暴力の根絶をしなければならない」と述べた。また、未然防止の具体策として、次の対策を求めたという。
・第三者の目が届きにくい環境を減らす
・教師と子どもの密室状態をなくす
・指導には教師らが複数で関わる
・カメラを置けないよう教室などを無作為に点検
この会議を踏まえて鹿児島県教育委員会は、県内にある市町村の各教育委員会に同様の指導をすることになる。
盗撮事件、垂水市に国と県への報告義務なし
ところが驚くことに、昨年9月に垂水市の公共施設で児童10人が被害に遭った盗撮事件については、この指導の対象にはなっていない。なぜなら、この公共施設の所管が垂水市教育委員会ではなく、垂水市保健課だからだ。
それゆえに垂水市は、盗撮事件について国と県に報告しておらず、すべて同市だけの判断で事後対応をしている。その結果、事件発覚から約10カ月が経った今現在でも、垂水市は被害児童やその保護者に謝罪することなく、市としての再発防止策も講じていないため、保護者有志から事件の調査や検証などを求める声が上がっている。

鹿児島県庁(中央)と鹿児島県警本部(右)=県ウェブサイトより
死亡または大けがのみ報告義務
県保健福祉部子ども政策局の子育て支援課によると、盗撮事件があった公共施設は児童福祉法に基づいて設置・運営されており、施設内で児童が死亡または全治30日以上の負傷をする「重大事故」が起きた場合は、県を通じて国のこども家庭庁に報告する義務がある。だが、今回のように公共施設で働く職員が盗撮事件を起こし、児童が被害に遭ったとしても、国と県への報告義務はなく、垂水市だけで事件に対応することになるという。
盗撮事件、なぜ児童施設は蚊帳の外なのか?
取材で子育て支援課長の説明を聞きながら、筆者は耳を疑った。
盗撮事件で児童が被害に遭ったのは全く同じなのに、なぜ垂水市の公共施設は蚊帳の外に放置され、国や県の指導を受けないままで済まされるのか。法律や制度のうえで、この公共施設が学校と異なる位置づけであることは理解できるが、盗撮の被害に遭ったのは、いずれも同じ児童である。そして、この公共施設は児童が学校での授業を終えた放課後に訪れる場所で、日常的に学校から連続するかたちで利用している。
保護者から見れば、子どもの安心安全を信じて預けるという意味では、この公共施設と学校は全く同じである。それにもかかわらず、盗撮事件が学校で起きれば国や県が指導する一方、この公共施設であれば垂水市に対応を一任するというのでは、保護者が納得するはずはない。

垂水市役所=鹿児島県ウェブサイトより
法律と制度の壁で垂水市に指導できず
子育て支援課長は取材に「学校とは法律や制度が違うので、垂水市で起きた盗撮事件への対応は市に任せるしかない」と言うが、今回のように垂水市が無責任な対応を続けている場合は、保護者はどうすればいいのか。法律や制度が壁になって、国や県が指導できないのであれば、その法律と制度に不備があるのではないか。
盗撮事件の被害に遭った児童とその保護者の身になれば、この公共施設も学校も、安心して利用できる場所でなくてはならない。そして、保護者から見て無責任な対応が続いているのであれば、国や県が垂水市に指導できるように、法律と制度を見直すべきである。
さらには、子どもが利用する児童館などの公共施設を所管するこども家庭庁は文科省と連携して、盗撮などの性暴力事件への対応を検討する必要がある。


南日本新聞記事3.jpg)