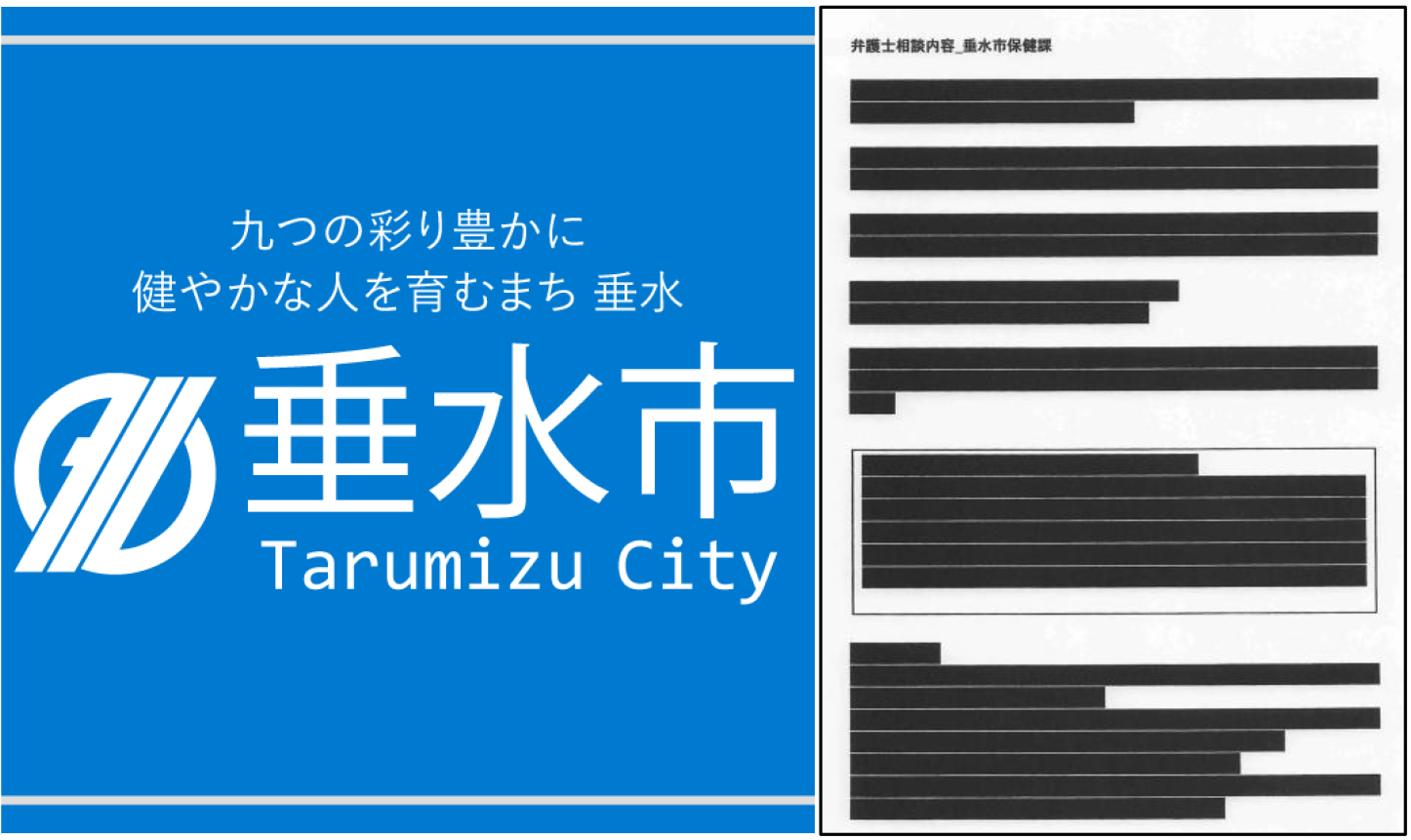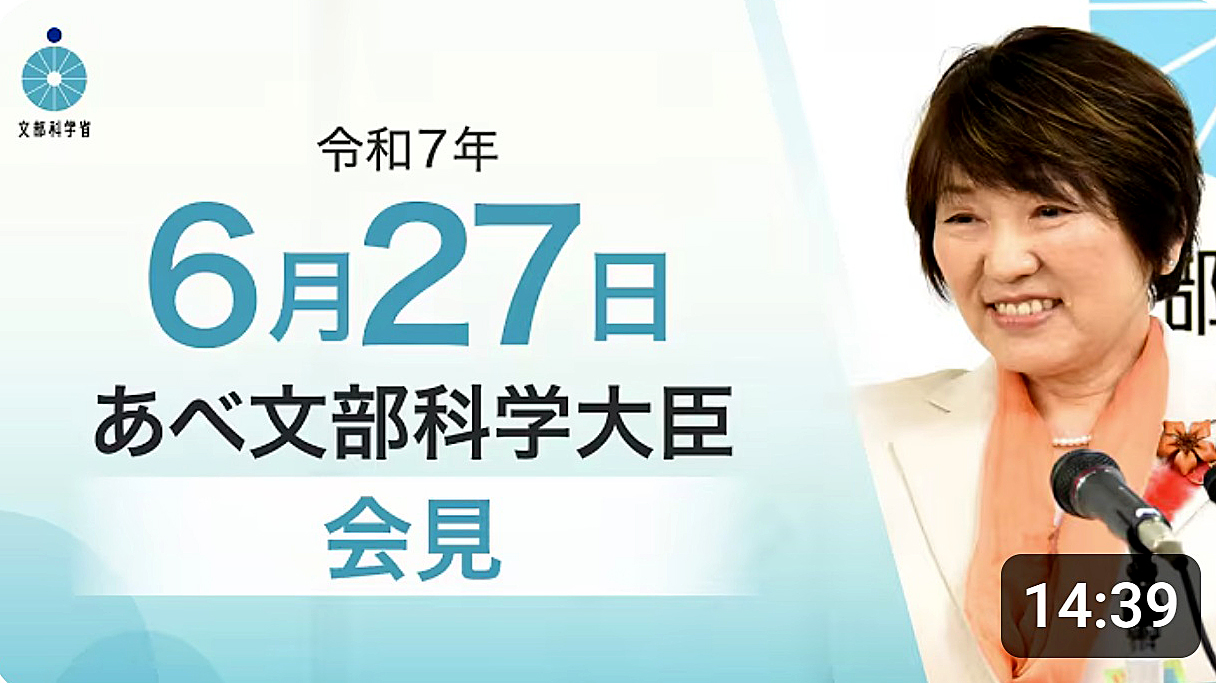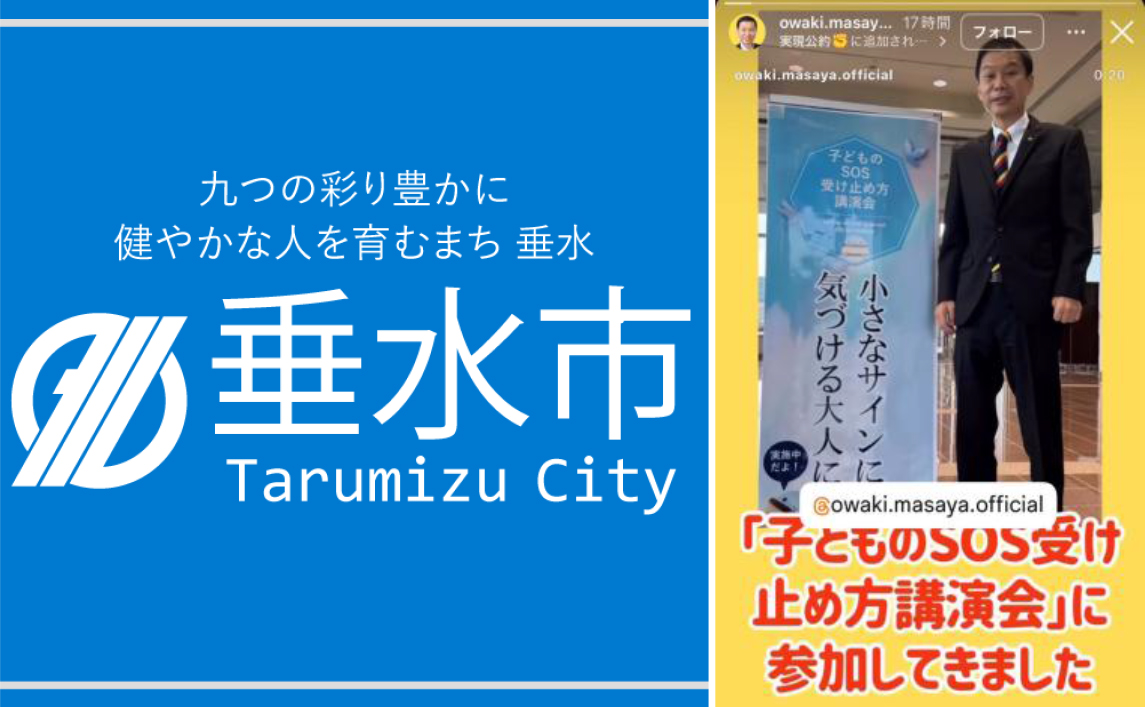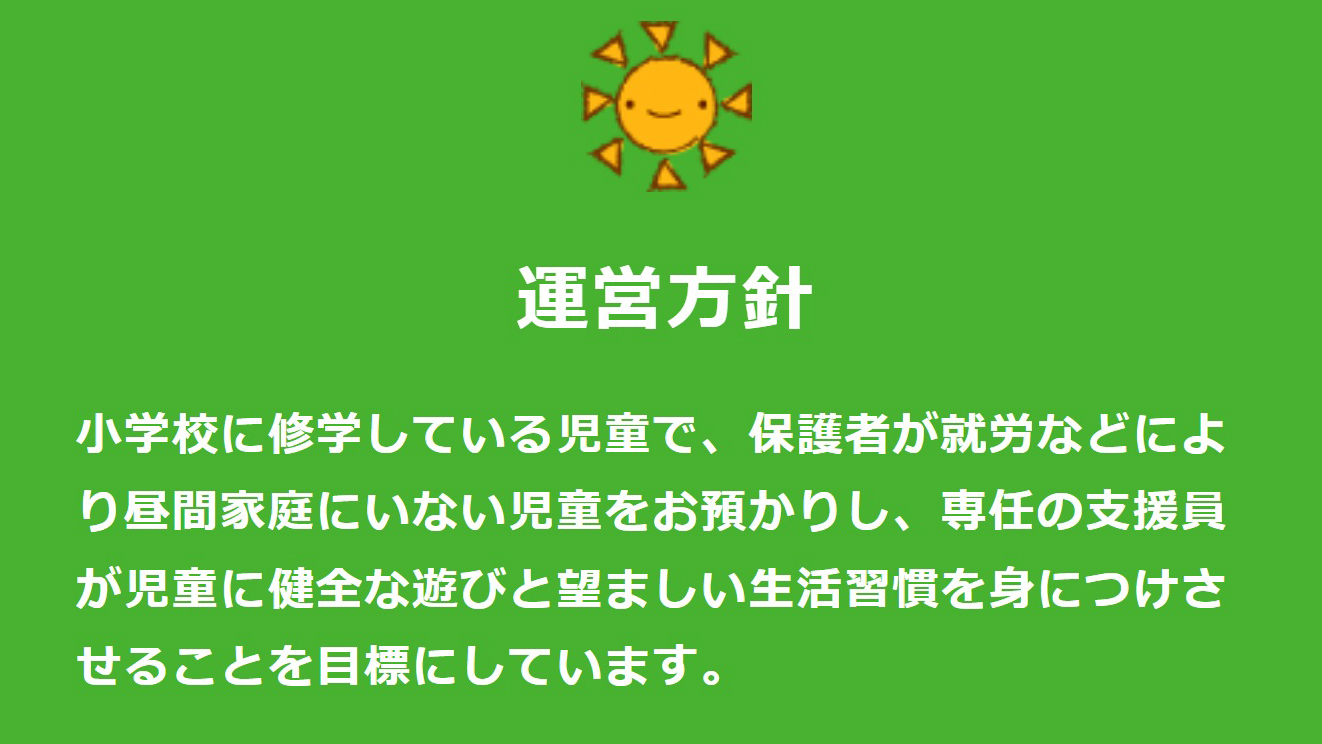【視点】児童盗撮、被害50人の可能性でも沈黙する垂水市/鹿児島ポスト
垂水市の公共施設、更衣室で盗撮を続け4年間 → 市委託先の職員、児童10人の盗撮で有罪 さらに40人も被害の可能性
保護者、被害者対応しない垂水市に不信感

【左】垂水市のウェブサイトに掲載された市のマークなど
垂水市の公共施設で起きた児童盗撮事件は、8月に入って新たな局面に入っている。刑事事件で被害が確定した10人に加え、さらに40人もの児童が被害に遭っていた可能性が明らかになったからだ。
この施設を設置する垂水市は、これまで「関係者の権利擁護」を理由に、事件があった事実を含めて、市民に対して一切の情報を公表していない。だが、計50人もの児童が盗撮被害に遭った可能性が出てきた以上、このまま沈黙を続けることは許されないだろう。
盗撮データ保存のPCなどを海に投げ捨てる
この事件で最も問題なのは、垂水市が業務を委託した公益社団法人の30代職員が、更衣室の壁に盗撮用のカメラを設置していたことを、約4年間も気づけないまま放置していたことだ。その間にカメラは1台から4台にまで増設され、児童が水着に着替える様子などが次々と記録されたのである。
2024年9月に事件が発覚したのち、その職員は過去の盗撮データを保存したパソコンやハードディスクなどを海に捨てたという。おそらくだが、新たに被害の可能性が判明した40人の映像は、そのなかに保存されていたと推察される。そして、その職員は約4年にわたり、それらの映像を「鑑賞」していたのであろう。
市委託先の法人、児童50人の保護者に被害弁償を提案
この事件の経緯を踏まえ、職員を雇用していた同法人は7月31日付で文書を送付し、児童50人の保護者に被害弁償の提案をしたが、突然の連絡に驚いている親御さんも多いに違いない。いきなり文書が届き、自分の子どもが盗撮の被害に遭った可能性があるので被害弁償したいと伝えられても、すぐには心の整理がつかないであろう。
そして何より問題なのは、被害児童とその保護者への対応を、これまで垂水市が同法人に一任してきたことだ。
市として再発防止策ないまま施設運営を継続
あらためて言うまでもないが、この事件が起きた公共施設を設置しているのは、垂水市である。この施設の運営業務を同法人に委託し、市民の公金から業務委託費を支出しているのも、垂水市である。そうであれば、事件に対する一定の責任は、同法人だけでなく、垂水市にもあるのは当然のことである。
それにもかかわらず、これまで垂水市は被害児童の保護者に謝罪せず、事件後の対応などについて説明することもなかったという。さらには、盗撮事件に対する調査と検証もしておらず、市としての再発防止策も講じないまま、いま現在でも公共施設の運営を続けている。

垂水市役所の庁舎=2025年8月5日撮影
保護者「こんな無責任な対応をされるとは」
盗撮被害に遭った児童が計50人になる可能性があると知り、8月初めに垂水市を訪ねてみた。そして、被害児童の保護者に取材をすると、聞こえてくるのは、垂水市に対する不信の声ばかりだった。
「垂水市の施設だから安心して子どもを預けていたのに、まさかこんな無責任な対応をされるとは思っていなかった」
「垂水市の公金で運営している施設なのに、どうして保護者説明会で市の幹部や職員が謝罪や説明をしないのか」
「垂水市として事件の調査や検証をせず、再発防止策も講じないまま、施設の運営を続けていることが、一市民として信じられない」
小中学校であれば国や都道府県が指導
今回、新たに被害の可能性が判明した児童40人の保護者には取材できていないが、おそらく垂水市の対応に不信感を抱いているであろう。
もし、これが公立小中学校での盗撮事件であれば、文部科学省や都道府県の教育委員会、各市町村の教育委員会が連携して対応や指導にあたり、再発防止や事件防止に向けて動くことになる。
だが一方で、今回の事件のように児童館などの公共施設については、こども家庭庁が国の所管となっており、法律と制度上、各自治体の教育委員会は全く関わりがない。そのため、施設内で刑事事件が起きた場合は、各自治体だけで対応することになる。
ところが、今回の垂水市の対応をみるかぎり、保護者が安心して子どもを預けられる状況にないことは明らかだ。保護者からみれば、文科省やこども家庭庁といった所管の違いは関係なく、自分たちが暮らす市町村を信じて、大切な子どもを預けているのである。
法と制度の見直しで安全安心な児童施設に
いま現在、児童館などの公共施設は、教育行政の蚊帳の外に置かれているが、児童にとっては小学校の放課後に利用する「地続き」の施設である。そうであれば、児童が安心して利用できる施設にするために、国や都道府県の目が届く施設運営ができるよう、法律と制度の見直しが強く求められる。