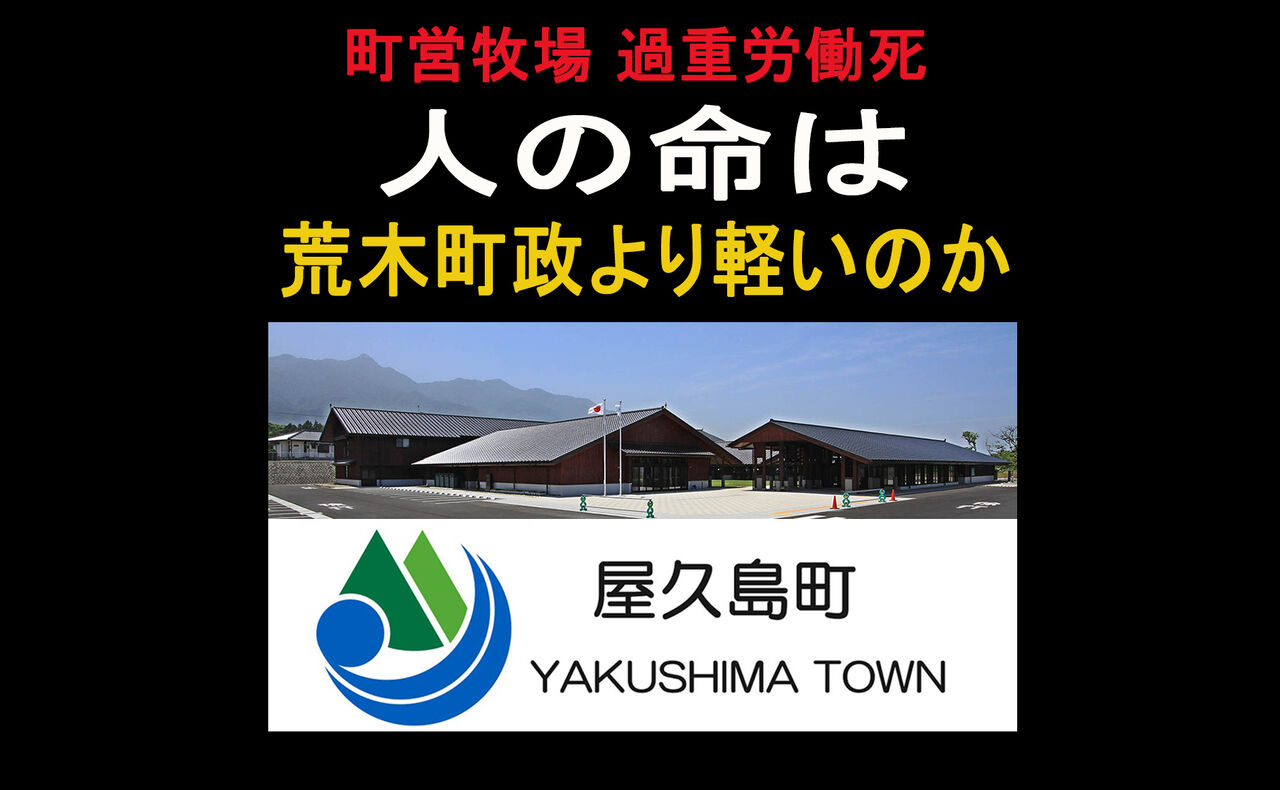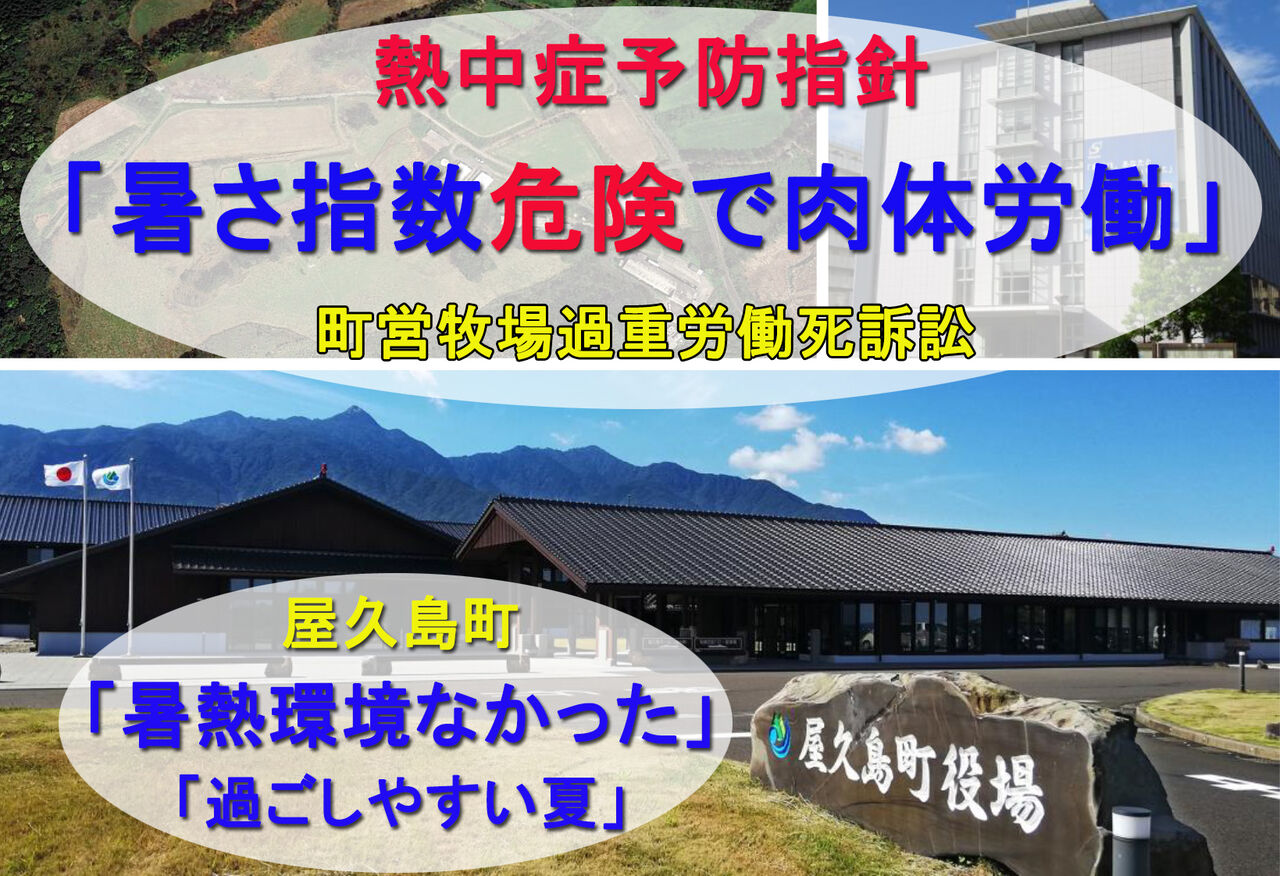【視点】屋久島町、町営牧場の過重労働死訴訟で方針一転の不思議/屋久島ポスト
町主張の根幹、職員は大した労働もせず体調不良で死亡 → 荒木町長、一転して和解の席に着く意向
公務災害の認定事実も完全否定だったが…

【左】裁判所から和解案が示されることを報告する屋久島町の荒木耕治町長=2025年6月9日、屋久島町議会【右上】屋久島町役場【右下】職員が過重労働で死亡した町営長峰牧場の衛星写真=Google Earthより
屋久島町営牧場で2019年8月、町職員だった田代健さん(当時49)が過重労働で死亡した問題をめぐる民事訴訟――。被告の町は6月の第9回口頭弁論で、和解を検討する意向を鹿児島地裁に示した。これを受け、同地裁は8月末までに和解案を示す予定だが、これまでの町の主張を振り返ると、なぜ町が和解の席に着く気になったのか、まったく理解できない。
そもそも町は、長時間にわたる労働の指示をしておらず、田代さんに「過重労働はなかった」との主張を続けてきた。さらに、田代さんには体調面で「高血圧症」や「長期の喫煙歴」などの問題があり、それらが大きな要因となって心筋梗塞を発症して死亡したとも指摘してきた。
つまり、田代さんは大した労働もしておらず、単に自身の体調不良で死亡したというのが、町の主張の根幹である。
公務災害、心筋梗塞による過重労働死を認定
それに対し遺族は、田代さんの死亡について、地方公務員災害補償基金の鹿児島県支部(支部長:塩田康一・鹿児島県知事)が過重労働で心筋梗塞を発症したことによる公務災害と認定したことを踏まえ、町が職員の勤務を適切に管理する安全配慮義務を怠ったと主張。さらに、町が実際より短い勤務時間を記録していたことなどから、長期間にわたって公務災害の申請ができなかった「申請阻害」も併せて、慰謝料や逸失利益などとして、町に対し約7000万円の損害賠償を求めている。
町「過重労働はなかった」の一点ばり
2023年10月の提訴から約1年9カ月、すべての裁判記録に目を通してきたが、町は遺族の主張だけなく、民間の労働災害にあたる公務災害の認定事実についても、真っ向から完全否定を続けてきた。労災が認定されれば、民間企業はその決定に従うのが一般的だが、町は公務災害を認めた同基金の見解をまったく受け入れず、「過重労働はなかった」の一点張りだった。
町と遺族、両者の主張がこれほど対立しているのであれば、判決で司法の判断を仰ぐというのが自然な流れである。それゆえに遺族は判決を望んでおり、和解の席に着くかどうかは明らかにしていない。
その一方、同町の荒木耕治町長は和解を検討する意向を示し、その旨を同地裁に伝えたというのだが、なぜ方針を一転させたのか、さっぱりわからない。あれほど頑なに「過重労働はなかった」と主張して、公務災害の認定事実を完全否定したのであれば、当然のごとく判決を望むべきところである。
定年退職した担当課長に一定の責任
ここからは推察になるが、町営牧場を所管する町産業振興課の課長が今年3月末に定年退職したことが、大きく影響しているのではないか。
訴状などによると、田代さんの同僚職員が2019年4月にこの課長と面談し、「仕事がきついので、職員を増やしてほしい」などと交渉したが、予算不足を理由に認められず、その4カ月後に田代さんが死亡したという。この主張に対し、町は「職員を増員するよう要請を受けたこともない」と否定しているが、公務災害で過重労働が認定されたことを踏まえれば、この課長には、適正な労働管理を怠った一定の責任があることは明らかである。
町の方針転換と担当課長の退職に、どのような関係があるのかは定かではない。だが、荒木町長が自ら和解の席に着く意思を示したということは、田代さんの過重労働死について、町が一定の責任を認めるということである。
早期に和解せず最大990万円の弁護士費用
この民事訴訟で町は、着手金として330万円を代理人弁護士に支払い、成功報酬の上限を660万円と決めている。だが、もし公務災害が認定された段階で、すぐに町が遺族と和解の交渉をしていれば、これほど多額の弁護士費用は必要なかった。
当然のことだが、判決確定後の賠償金または和解成立後の解決金、そして弁護士費用は、その全額を屋久島町民の公費で負担することになる。判決や和解の内容にもよるが、もし荒木町長や担当課長らに重大な過失を認めるものであれば、公費ではなく、それぞれの責任で負担すべきではないか。